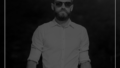太宰治という作家の名前を聞いたとき、わたしたちの多くは「心中」という言葉を思い浮かべるのではないでしょうか。実際に彼は生涯の中で何度も女性を巻き込んだ心中未遂を繰り返し、最終的には玉川上水で愛人と命を絶ちました。その結末はあまりにも有名であり、彼の文学作品と切っても切り離せないものとして語り継がれています。
けれども、占星術の観点から太宰治を見つめると、単なる「破滅型作家」のイメージ以上に深いテーマが浮かび上がってきます。そこには海王星の濃厚な影響と、12ハウスに象徴される閉ざされた世界観が色濃く刻印されているのです。
■名家に生まれながら問題児
太宰治、本名・津島修治。1909年に青森の名家に生まれました。父は貴族院議員を務め、経済的にも社会的にも申し分のない環境。まさに「勝ち組」と言っていい立場だったのです。しかし彼は、若年期から精神的に不安定で家族を大いに悩ませました。左翼思想に傾倒し、シンパを匿って警察にマークされるなど、社会的にも危うい行動を繰り返します。
1932年になってようやく左翼活動から離脱しましたが、それまでの間は「超」がつくほどの問題児。家の地盤を継いでいた兄は奔走し続け、家族の頭痛の種だったと言えるでしょう。
■レクティファイから見える太宰の星
わたしは彼の出生図をレクティファイしてみました。その結果見えてきたのは、海王星の強烈な影響です。アセンダントを蟹座に設定すると、海王星がアセンダントに重なり、しかも12ハウス寄りに位置します。この配置は「現実感覚の薄さ」「夢や幻覚に包まれる資質」を強め、地に足のつかない生き方を誘発します。
さらに、太陽、月、水星、金星、海王星、冥王星が12ハウスに集結することになります。これはまさに「12ハウスのマジョリティ」。12ハウスは潜在意識、隔離、逃避、秘密、そして自己破壊を象徴します。そこにライツ(太陽と月)や個人天体が集まることで、彼は「自分の中の闇」と常に向き合わざるを得なかったのです。
■月と金星の蟹座OOB
太宰の月と金星は蟹座で、しかもOOB(アウト・オブ・バウンズ)に位置していた可能性があります。OOBは通常の天体の運行範囲を外れ、極端な性質を発揮する配置です。月と金星が蟹座にあること自体、家庭的で母性的な要素を持ちますが、OOBとなればその感情の波は常軌を逸しやすくなります。女性の心を掴む独特の魅力もそこに由来するのでしょう。多くの女性が彼に惹かれ、そして破滅的な関係に巻き込まれた背景には、この月と金星の異常な光り方がありました。
■火星と文学的衝動
太宰の火星は9ハウスにありました。9ハウスは精神性や哲学、宗教、学問、海外を象徴します。火星がここにあると「精神的な戦い」に熱を注ぐ傾向があります。彼が文学を通して人間の死生観や存在の意味を問い続けたのは、この火星の位置と無関係ではありません。小説家としての情熱は、ただの職業的表現ではなく「生きるか死ぬか」に直結するものであったのでしょう。
■土星の影と死生観
10ハウスには土星が在室していました。土星は抑圧、制限、重荷を象徴します。社会的な立場の重圧を幼少期から背負い、「死」というテーマに独自の哲学を抱いた背景には、この10ハウス土星の影響があると考えられます。名家の子息としての責任と、作家としての自由な魂との間で引き裂かれるような葛藤を抱え続けたのです。
■心中の瞬間と占星術
最期の心中事件を占星術的に見ると、ネイタル火星にソーラーリターン土星が合を形成していました。火星と土星の合は「行動の抑圧」「理由なき憂鬱」を示す典型的な配置です。まるで宇宙から「ダメ出し」を食らっているような感覚に陥る時期。本人の意志とは関係なく、心が沈み込みやすいのです。
さらにソーラーリターンの天王星は8ハウスにありました。8ハウスは死と再生を司り、天王星は「予測不能な衝撃」を象徴します。この配置は「死に関する衝動的な行為」を示唆しているとも読めます。彼が妻に不満を持っていたわけではなく、ただ「動かずにはいられなかった」のです。天王星はアクセルとブレーキを同時に踏む惑星。だからこそ破滅的な行動に走るのです。
■女性と共に迎える死
太宰は「女性と共に死ぬ」ことに強烈なこだわりを持っていました。それは彼の12ハウス的な資質が、自己破壊と共依存を不可避にしていたからです。女性との結びつきに救済を求めながらも、それを同時に破滅へと引きずり込む。まさに相反する欲求の狭間で揺れ続けたのです。
海王星は夢や理想を象徴しますが、同時に幻惑や逃避をもたらします。彼の場合、月と金星と海王星が結びついていたため、女性との関係を通して「夢」と「破滅」が同時に展開されることになりました。けれども同じ配置を持つ人が皆心中するわけではありません。太宰の場合、12ハウスに天体が集中していたこと、そして社会的立場や時代背景が絡み合って、その衝動が現実化したのです。
■死生観という膨張したテーマ
太宰にとって「死」は単なる終わりではなく、生の裏面にある必然でした。生きづらさを抱え、現実を直視できず、夢と幻想に逃げ込みながら、それでも文学を通して「死」を語り続けたのです。彼にとって死は「非業」ではなく「人生の構造そのもの」でした。
月と海王星の合は、現実的な感覚を受け入れにくく、常に夢や妄想に支配されやすい配置です。わたし自身もこの配置を持つため、彼の「現実逃避的な感性」には強い共感を覚えます。時に非合理で、時に危うく、けれども人間の心の深層に触れる力があるのです。
■おわりに
太宰治を単に「心中の常習犯」と片付けるのは容易です。しかし占星術的に見れば、彼は海王星と12ハウスに翻弄された魂であり、死を通じてしか自己表現を貫けなかった存在でもあります。多くの女性を巻き込み、多くの人を傷つけたのも事実ですが、その根底には「生きることそのものの苦痛」と「死に魅せられる魂の構造」がありました。
太宰を読み解くことは、わたしたち自身の「生と死」を考えることに直結します。彼の星を見つめながら、わたしたちもまた、自分自身の内側に潜む夢と幻想、そして死生観と向き合わざるを得ないのです。