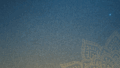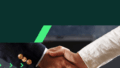オープンチャット「タラッサ魔麻〜星を味方にする!〜」
↑こちらクリックしてね
地球には月がひとつだけ。そう思い込んでいる人間は、まずその固定観念を手放した方がいい。学校教育で刷り込まれた常識など、宇宙の前では紙切れより軽い。今回の準衛星PN7の発見は、その薄っぺらい常識を粉砕してくれる格好の材料だ。
PN7という天体は、私たちの誰もが知らないまま、六十年ほども地球の横でしれっと並走していたという。にもかかわらず、ようやく人類が気付いたのが二〇二五年の夏というお粗末さだ。六十年だぞ。六十年も、地球はこの小惑星とずっと一緒に太陽を回っていたのに、誰も気付いていない。鈍いにもほどがある。
メリーランド大学の天文学者、ベン シャーキーはPN7についてまた見つかったか、クールだな、くらいの軽い反応をしている。この落ち着きぶりは、地球の近くには常にこういう小さな天体がうじゃうじゃいるという事実を、彼ら天文学者だけが理解していたからだ。一般人だけが取り残されていたのである。
準衛星とは何か。この名称に惑わされる人が多いが、準衛星は地球の衛星ではない。太陽の周りを回っている小惑星だ。しかし地球と同じような周期と軌道で動くため、あたかも地球の周りを回っているように見えてしまう。要するに、地球のストーカーのように寄り添っているくせに、本命は太陽なのだ。なんとも扱いづらい関係性である。
本物の月は、地球の重力に完璧に捕まえられている。それに対し、準衛星は捕まっているふりをしながら実は地球のことなど大して気にしていない。自分の都合だけで太陽の周りを一定のリズムで回り、その動きが偶然地球の軌道と重なるため、あたかも仲良く並走しているだけである。
さらに準衛星の仲間には、ミニムーンと呼ばれる存在もいる。こちらは地球に一時的に捕まって、本当に地球の周りを何度か回ってから去っていく。ちょっと家に泊まって、気が済んだら出ていく友人のような存在だ。地球は都合よく利用され、ミニムーンは勝手に出ていく。宇宙というのは、時に情のない関係性ばかりである。
では、なぜ六十年も存在した天体を見逃していたのか。理由は簡単だ。小さい、暗い、速い。この三拍子が揃っているからだ。人間の目では到底追えない。強力な望遠鏡で、暗闇で反射するわずかな光を拾わなければ見えない。夜空に堂々と現れる本物の月とは比べ物にならないほど地味である。
PN7はビルほどの大きさしかない小惑星だ。表面も暗く、光をほとんど返さない。そんなやつが地球の横を猛スピードで飛んでいるのだから、見つからない方が正常だ。技術が追いついた今になって、ようやく発見が続いているだけのことだ。
こうした天体たちが見つかるたびに、地球には思っている以上にたくさんの月があるという事実を突きつけられる。地球と並走する者、ふらりと立ち寄って去る者、ずっと隠れている者。宇宙は予想以上ににぎやかだ。私たちが勝手に静かな宇宙を想像していただけで、実際はずっと雑然としている。
準衛星やミニムーンは、ただの珍しい天体ではない。太陽系の歴史を語る証拠品でもある。彼らの軌道は、太陽系内部で起きた衝突や散乱の痕跡だ。小さな天体の軌跡は、太陽系の古い手紙のようなものだ。そこには過去の大事件の痕跡が残されている。
また将来の宇宙探査においても、準衛星という存在は重要になる。月に行くより燃料が少なくて済む小規模な探査の拠点になる可能性もある。資源採取の候補にもなり得るだろう。地球の近くを漂う小さな岩石が、大きな未来の扉を開くかもしれないのである。
ただし、ここで一番面白いのは、人間の思い込みの軽さが暴かれた点だ。地球には月がひとつしかないという常識は、ただの思い込みにすぎない。実際には、地球の周りには何十年も前から小さな相棒が何体もいた。それに気付いていなかったのは人間の方だ。宇宙はとっくににぎやかだった。
PN7は名前こそ地味だが、その存在が教えてくれた真実は非常に大きい。地球の周りは空っぽでも何もないわけでもない。静かに寄り添う仲間たちがいた。それを知らずに偉そうに月はひとつです、などと語っていた私たちの方が無知だったのだ。
宇宙は黙っていても、人間の常識を裏切ってくる。その裏切りこそが、宇宙の最大の魅力だ。地球は一人ではない。太陽系はもっと雑で、複雑で、そして面白い。PN7はその事実を皮肉なくらい静かに示してくれた。
地球にはもっと月がいる。それを知った瞬間、世界は広がる。太陽系は私たちが考えていたよりずっとにぎやかで、生き物のように動いている。この新しい視点を手に入れた時、人間の常識などいかに小さいかがよく分かる。
これが、準衛星PN7が突きつけた現実である。